インフルエンザの季節到来!正しい知識で予防と対策を
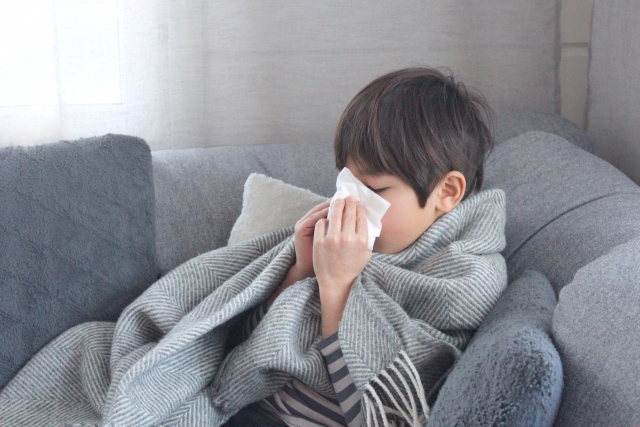
インフルエンザとは
インフルエンザは、インフルエンザウイルスによって引き起こされる急性の呼吸器感染症です。通常、「季節性インフルエンザ」と呼ばれる型が、毎年冬季に流行します。主にA型とB型が人に感染し流行を起こします。風邪に似た症状から始まりますが、全身のだるさや高熱、頭痛、関節・筋肉痛などが強く、症状の現れ方が急なのが特徴です。一般的に健康な人では自然に回復することも多いですが、小さな子ども、高齢者、持病のある方などでは、肺炎や脳症など重篤な合併症を起こすリスクがあります。当院では予防接種や早期診断・適切な治療を通して、インフルエンザの重症化を防ぐことを重視しています。流行期には患者さんご家族への情報提供を強化し、感染対策の徹底を呼びかけています。
インフルエンザの感染経路
インフルエンザは主に「飛沫感染」と「接触感染」の2つの経路によって広がります。感染している人が咳・くしゃみをした際に放出された飛沫を他人が吸い込むことが飛沫感染です。また、飛沫が周囲の物品(ドアノブ、手すり、テーブルなど)に付着し、その物を触った手で口や鼻、目などの粘膜を触ることで感染する接触感染も重要です。さらに、症状が現れる前や発症初期にもウイルスの排出があり、症状が軽いと本人も気づかないまま周囲にうつしてしまうことがあります。人が集まる場所や密閉・換気の悪い空間では感染リスクが高まるため、咳エチケットやマスクの着用、手洗い・手指消毒、定期的な換気が有効な予防策です。
インフルエンザの潜伏期間
インフルエンザに感染してから症状が現れるまでの期間、いわゆる潜伏期間は通常1〜3日程度が多いとされています。ただし、個人差があり、免疫力やウイルスの種類(A型またはB型)によっては1日未満で症状が出ることもあれば、または4日ほどかかることもあります。また、潜伏期間中でも感染力が完全にないわけではなく、発症前日からウイルスを排出するケースが報告されており、他者への感染の可能性があります。
インフルエンザの症状
インフルエンザにかかると、潜伏期間(平均1〜3日)の後、急に高熱(38℃以上になることが多く)、悪寒、激しい頭痛、全身の筋肉痛・関節痛、倦怠感などの全身症状が現れます。次いで、のどの痛み、咳、鼻水などの呼吸器症状や、時には鼻づまりなどもみられます。小さな子どもでは中耳炎を併発することや、喘息の発作を誘発することもあります。高齢者や基礎疾患を持つ方では肺炎などの合併症が起こりやすく、命に関わるケースも稀ではありません。症状はおよそ5~7日程度で軽快することが多いですが、全身の疲れが残ったり、症状が長引くこともあります。医療機関での診察・治療が重要です。
インフルエンザとかぜの違い
インフルエンザと一般的な「かぜ(風邪)」は、原因ウイルスや症状の出方に違いがあります。かぜは多くの種類のウイルスが原因で、のどの痛み・くしゃみ・鼻水などの上気道症状が中心となることが多く、熱があっても軽めであることが多いです。一方、インフルエンザは発病が急激で、高熱、筋肉痛・関節痛・頭痛・全身倦怠感などの全身症状が強く出ることが特徴です。症状の重さと急速な経過、合併症のリスクの点でもインフルエンザのほうが重くなる傾向があります。また、かぜは自然に回復するケースがほとんどですが、インフルエンザは予防接種や適切な抗ウイルス薬などの治療が重症化を防ぐのに有効です。どちらも似た症状がありますので、流行期には症状が強い場合はインフルエンザを疑う必要があります。
| インフルエンザ | かぜ | |
| 原因 | インフルエンザウイルス | ライノウイルス、コロナウイルス、アデノウイルスなど |
| 流行時期 | 主に冬季(11月~3月頃) | 年中発生(特に季節の変わり目) |
| 発症 | 急に高熱・全身症状が出る | ゆるやかに症状が始まる |
| 熱 | 38℃以上の高熱が多い | 発熱は軽度か、ないこともある |
| 全身症状 | 強い倦怠感、頭痛、筋肉痛、関節痛が出やすい | のどの痛み、鼻水、くしゃみが主 |
| 予防 | ワクチン接種、手洗い、マスク | 手洗い、うがい、休養 |
| 治療 | 抗インフルエンザ薬(発症早期のみ有効)、安静 | 対症療法(解熱剤や咳止めなど) |
インフルエンザの予防

インフルエンザの予防にはいくつか方法があります。まず、毎年の予防接種(ワクチン接種)が最も効果的であり、特に子ども・高齢者・持病をもつ方は重症化予防のためにワクチンを推奨します。 また、マスク着用、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に口と鼻を覆う)、手洗い・手指消毒の徹底も大切です。生活習慣の点では、十分な睡眠、バランスの良い食事、適度な運動により免疫力を保つことが助けになります。流行期には人混みを避け、室内の換気をこまめに行うことも予防になります。家庭内で感染者が出た場合は、共有物の消毒やタオルの分け合いを行い、マスクをするなどして他の家族への感染を防ぎます。
インフルエンザの検査
インフルエンザの診断は通常、発熱や咳・のどの痛みなどの症状から医師が臨床的に疑った上で行われます。迅速検査キットを使用し、鼻やのどからの拭い液やぬぐい液を採取してウイルス抗原を検出する方法が一般的です。これにより、発症早期でも比較的短時間で診断可能です。ただし、感染直後ではウイルス量が少なく検査で陰性になる場合もあり、症状や流行状況から「インフルエンザ様疾患」と診断されることもあります。必要に応じて、追加検査や重症化リスクのある人には詳細な検討が行われることがあります。当院では、症状の強さや経過を見ながら、適切な検査を提案しています。
インフルエンザの治療
インフルエンザの治療は、症状を抑える対症療法と、場合によっては抗ウイルス薬の使用が中心となります。発症早期(できれば症状出現から48時間以内)であれば、抗ウイルス薬を使うことで症状の期間を短くし、重症化や合併症を予防できる可能性があります。熱が高いときは解熱剤を使い、のどの痛み・咳・鼻水などに対してはそれぞれに合った薬を使用します。十分な水分補給や休息も非常に重要です。乳幼児や持病のある方、または症状が急速に悪くなるような場合は、入院治療が必要になることもあります。当院では、患者さんの年齢・症状・基礎疾患の状況を見て、最適な治療計画を立て、必要であれば専門医と連携して対応します。
大田区、目黒区、東急目黒線沿い(田園調布、奥沢、大岡山、洗足、西小山、武蔵小山など)、東急大井町線沿い(自由が丘、緑が丘、大岡山、旗の台など)で予防接種をご希望方はぜひ一度、大岡山こどもアレルギークリニックへご相談ください。
